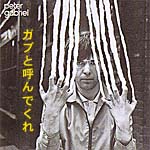
[08]あなた、“ピーター・ゲイブリエル”って呼びます?
ねぇ、そうやって“げいぶりえる”って言ってます? イヤだなぁ、そんなの……。僕は“ガブリエル”。ちなみに大槻ケンヂも“ガブリエル”。なぜなら、彼は“ピーガブ”と略すからだ(ゲイブリエルでは“ピーゲブ”とか“ピーゲイブ”だとかって妙な省略になっちゃうなぁ)。いつからこんな呼び方になったんでしょうか。英語の発音により近く表記するのはいいけれど、慣れ親しんだ呼び名をわざわざ故意に言い換える必要があるんだろうか。“エイジア (ASIA)”のように初めっから発音表記してあれば馴染んでいるから違和感はないんですが、──“アジア”じゃ、なんか素っ気ないもんね──、誰の策略か突然恣意的に変えられると落ち着かないなぁ。
最近では“クイーンズライチ (QUEENSRŸCHE*)”がそう。一昨年のニュー・アルバムでいきなり“クイーンズライク”なんてなってる。もう十数年にもなるベテラン・バンドにどうしてまたこう語呂の悪い呼び方になるんでしょう? 「ビジネスライク」の親戚みたいで全然ヘンだ。長年のファンにとっては偽物バンド、あるいはパロディ・バンドだと思っちゃう。レコード会社が変わったんで版権の問題でもあったんだろかとか、縁起でもかついだんだろかとか要らぬ憶測をしてしまいます。
アイルランドのバンド“イオナ (IONA)”の場合も同様だ。イオナ名義で4枚もアルバムを出しているのに、いつの間にか“アイオナ”っていう“エイジア読み”に変わっちゃっていました。そんなことも知らずに、友人から「アイオナが来日するんで行かない?」っていうメールを読んだとき、「そんなバンド知らん」といって断ってしまった。あとで話を聞けば、イオナのことをさしていることが判明。僕はアイオナなんて呼びたくない。なんかアフリカのマラソン選手みたいでそぐわない。イオナでCD買ったんだから……。
まあ、とは言ってもレコード会社がそう表記するんなら仕方がないって諦めざるを得ないんだけど、もっと胡散臭いのは「評論家諸氏がめいめい勝手に表記する」ときだ。未だに呼び方が定まっていないのはゴングのドラマー“ピエール・ムーラン (PIERRE MOELREN)”。最もポピュラーなのが“モエルラン”ですが、昨年の紙ジャケットで再発したゴングの日本盤解説では“モウラン”などと聞き慣れない表記をしている。ややもすると別人だと思ってしまいそうです。いったいどういうことになっているんでしょう。プログレ評論家達はこんなメジャーな人の読み方くらい統一しようという気も無いのでしょうか。評論家協会でも組合でも設立して、コンセンサスを作ってくれって言いたくなっちゃうな。
僕は“ムーラン”にしている。フランス語の知識なんか全然ないけれど、この呼び方が一番シックリくるし格好がイイっていう単純な理由からです(ちなみにディズニーのアニメ映画「ムーラン」は“MULAN”です)。ただ英語圏以外の人名を日本語表記するのはやや難しいのかもしれません(ピエール・ムーランはフランス人)。ドイツのクラウス・シュルツが“シュルツェ”になったり、ホルガー・チューカイを“シューカイ”と言ったり。フランスのパルサーは“ピュルサー”となり、タイフォンは初め英語読みの“タイフーン”と表記していたらしいし。このくらいならまだ許しましょう。
ところが、「そんなのどうでもいいだろっ!」てツッコミたくなるのは、超メジャーなバンドに対しての評論家の“こだわり”だ。ある雑誌では、キング・クリムゾンをわざわざ“クリムズン”と表記している評論家がいた。またキース・エマーソンを“エマースン”。そのくせディスク・レヴューでは“クリムゾン”“エマーソン”と通常表記となる(レコード表記がそうだからです)。ここまで来ると評論家のこだわりというよりも、自慰的行為としか思えません。(アコースティック・ギターを“アクースティック”という輩もいた。ア〜ア〜、ウットーシイッ!)
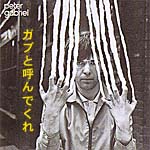 |
| 『ピーター・ガブリエル II』 |
何故、違和感のある表記をするのでしょうか。何故したがるんですか。このへんの意向が僕には全然理解が出来ません。話を元に戻しますと、“ぴーたー・げいぶりえる”ってやっぱり馴染めないんですよね。だって、実は、今でも、レコード会社は“ピーター・ガブリエル”なんだからっ!