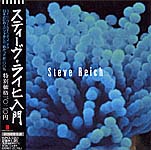
[03]スティーヴ・ライヒを知る。
10枚組ボックス・セット『ワークス 1965-1995』にて。
スティーヴ・ライヒという人に関して、名前だけは知っていました。現代音楽家ということだけは。
それが今年の8月になってベスト盤『スティーヴ・ライヒ入門』(なんと1,020円!)を購入し聴くことになりました。何故かというとステレオラブのCDのライナーノーツでミニマル・ミュージックとそのミュージシャン達が頻繁に引き合いに出されていたからです。スティーヴ・ライヒ、フィリップ・グラスからノイ!、カンなどのミュージシャンが上げられていました。このときはミニマルという意味も知りませんでした。ただ、短い小節を反復することなのかな、ということだけはうっすらと感じていました。
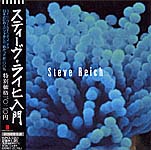 |
| 『スティーヴ・ライヒ入門』 |
ベスト盤には[クラッピング・ミュージック][エレクトリック・カウンター・ポイント][ディファレント・トレインズ][ドラミング][六重奏曲]というライヒの代表的な曲の抜粋が収録されています。聴くと不思議なループに落ち着くような、神経に触るような。夜、MacをいじっているときなどにBGMとして流しているうちになんとなく惹き込まれていきました。
そしてCDジャーナルの12月号にライヒが所属するノンサッチ・レコードのカタログが別冊で付録されていたんです(ちなみにこのレーベルには他にフィリップ・グラスやジョン・ゾーンなどがいます)。何故この時期に…しかも定期購読している雑誌に…別冊として付録していたか…私にはこれを運命と思わずにはいられませんでした。
ページを繰ってライヒのディスコグラフィーを眺めてみて、どれから手を付けていいか分からなくなり、エイヤッと10枚組ボックス・セットの『ワークス』を買ってしまうことにしました。
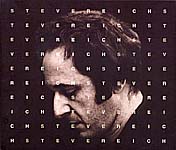 |
| 『ワークス 1965-1995』 |
まだ全部は聴いていません。
今のところ[ディファレント・トレインズ]が一番気に入っています。これは1988年クロノス・カルテット(アメリカの弦楽四重奏団)のために書かれた作品です。第二次世界大戦前後の状況下での列車の様子を弦楽四重奏が時には意気揚々と、また時にはヒステリックに表現しています。そのループの中で、乗客の言葉の断片の数々を演奏にからませていきます。単なる人の声と思っていたのですが、サンプリング・マシンを使って音程を持たせているらしいのです。
余談ですが、かのフランク・ザッパはスティーヴ・ヴァイがバンドに加入したとき「人の声を採譜しなさい」と命じたと言います。その後ヴァイはギターで会話っぽく演奏していることがよくあります。そういえば、エイドリアン・ブリューも動物の鳴き声をギターで鳴らしているっけ。そんなことをふと思い出してしまいました。
ライヒを聴いていてもう一つ思うことがあります。
キング・クリムゾンが80年代に再結成した頃は、“ミニマル”という言葉はロックフィールドでそれほどメジャーではなかったように記憶しています。当時はクリムゾンのポリリズミックなシーケンスにも驚いたものですが、そう考えるとライヒの先進性が偉大に思えてきます。
最後にこのボックス・セットの日本人解説者を紹介しておきます。
それが結構ユニークな面々で、細野晴臣、坂本龍一、巻上公一、石野卓球、ピーター・バラカンなどは想像に堅くないのですが、意外なところでは夏木マリ、中谷美紀が一筆とっています。中でも中谷美紀さんの解説は秀逸です。深夜、迂闊にも、全身に鳥肌を立ててジーンときてしまいました。とても綺麗な文体で、この短い文章だけで私はこの女性に好意を持ったばかりか、惚れてしまいました。
淡くも切なくライヒに夢中になったんだなぁ、と思わず感情移入しました。
長くなりました。勝手ながら中谷美紀さんのライナーノーツを全文転載させていただき、終わりたいと思います。